僕は半農半X的生活を求めて、都会ではないどこかを彷徨っているものです。
こんなふうに自分を紹介することもある。
そして、僕の半農には3つあります、と続ける。
ひとつ、上山棚田団。
ふたつ、箕面マイファーム。
みっつ、綾部の半農半X田んぼ。
今年は綾部の1000本プロジェクト田んぼはお借りしていない。それでも、半農半X研究所主任研究員として、脱穀とコナギ取りの手伝いはした。
静かな里の秋空の下で、塩見直紀さんと農作業をするのは至福の時である。
久しぶりに「里山ねっと・あやべ」に泊まれば思索が深まっていく。
考えるということは、穂を垂れた稲の下に潜り込んで実りを刈っていく行為に似ている。
ひたすら鎌を進めていけば、いつかは視界が開けることもある。霧が光に溶けこんでいくように。
今、僕が考えているのは、田中文脈研究所をどのように定本化していくか、という課題である。
塩見さんが提言している「一人一研究所のススメ」にしたがって設立した当研究所。その研究レポートは膨大な量になっている。400字詰め原稿用紙に換算すれば790枚を超えつつある。
定本化作業は地道にやるしかない。WEB上のテキストを縦書きに移しかえて写真をレイアウトしていく。田んぼに残されたコナギの根を一本一本掘って土を綺麗にしていくように。
時間がかかる。だが、この原稿を読んでくれる人はもっと時間と労力がかかるはずだ。できるだけ丁寧にやるしかない。
電通を早期退職して4年になる。書き連ねてきたことをひと繋がりにしていくと、分かってきたことがある。
僕は、半農半Xというコンセプトに導かれて、その背後に広がるコンテキスト(文脈)を探求するために動いているのだ。
さらに今年の半農には「善通寺田んぼ」という丸亀高校文脈も加わった。
また、夏の里山を流れる川でしかできない鮎釣りだって「半農」の文脈に繋がっている。水脈かもしれないが。
里山の川は農に直結している。川のそばには田んぼがあり畑がある。
半農半Xの基本的心構えである「センス・オブ・ワンダー(自然の神秘さや不思議さに目を見張る感性)」は川でも磨かれる。
僕の半農については、他人に分かるように説明する自信はある。
では半Xはどうか?
僕は半農半コンテキスターです、と言い続けてきた。
コンテキスターとは何か?
文脈家です。文脈を繋いで物語をつくる者です。詳しくはグーグルで「コンテキスター」と検索してみてください。そこには僕しかいませんから。これも僕の自己紹介の一パターンだ。
それはそれで自分の中では納得感がある。だが、他人が分かってくれているのかどうかは自信がなかった。
そんな気持ちのまま、相変わらず自由を友として動き回っていた。
そして、文脈原稿を整理しているうちに、自分の半Xの新しい考え方が見えてくる。
僕の半Xとは何か?
XはあくまでもXなのだ。
それは未知でありクロスである。関係性であり交錯である。
僕は「半農半X家」。
半農半Xか? と疑問形に聞こえないように発音しないと。
半農、すなわち小さな農をベースにして自分の天職、すなわちXを探していくのが「半農半Xという生き方」である。
たとえば、「半農半歌手」「半農半NPO」「半農半医」「半農半祈り」……。
ならば、Xを天職とする生き方があってもいいはずだ。
関係性を探究して、その交錯を楽しむ生き方。それを型として工作していく生き型……。
フミメイと呼ばれはじめてから現在まで、様々なことを見て聞いて、書いたりしゃべったりしてきたのは「半農半X家」としてのミッションだったのかもしれない。
上山棚田団での関係性は、右も左も上も下も交錯して〝複雑形X〟の宝庫になっている。
そこでのフミメイは固有の「楽しいことは正しいこと」というプリンシプルにしたがって動いていくしかない。
マイファーム箕面のフミメイ農園は15平米の有機栽培を文系百姓として続けている。
そこで始まった野菜縁脈は、自然栽培も交錯して様々な関係性を耕作しつつある。京都の日吉、島根の松江や山王寺と〝草の根X〟のエリアは拡大している。
綾部のXは明解だ。そこには塩見直紀さんがいるから。
田んぼを渡る風は、一定の方向へ吹き抜けていく。それは未来圏から吹いてくる颯爽とした風である。
〝あとから来る者のためのX〟が綾部にはある。
「半農半X家」という妙な言葉を主任研究員が勝手につくっていいものかどうか、疑問は残る。
ただ、Xに何をあてはめるかは〝使命多様性〟に基づき、人それぞれである。
ならば、Xに〝クロスして交錯すること〟をあてはめる変わり者がいてもいいはずだ。
「半農半Xカー」であるフミメイ号は、この4年間で86000キロを走破している。地球を2周以上。
「半農半X家フミメイ」は動いた距離に裏付けられている。自分の足と手でXを掴み取るための研究はしてきたつもりである。
君は半農半Xか? はい、自分は半農半X家であります。
最近、当研究所のレポートはやたらと長いものになっていた。
ブログという情報発信方式では、どうしても自分の語りたいことを一方的に届けることになってしまう。それでは読む方も大変だ。
文脈研究所の設立当時は、適度な原稿量であったと思う。原点に戻ろう。
今月は、定本・田中文脈研究所の章立て案をレポートして脱稿なのだ。
第一章 脱藩カウントダウン
第二章 《自立》する日々
第三章 そして311、アンガージュマンする日々
第四章 交錯し考察する日々
第五章 転がり続けて物語る日々
第六章 踊り場の日々
(以下未定)
こんなふうに自分を紹介することもある。
そして、僕の半農には3つあります、と続ける。
ひとつ、上山棚田団。
ふたつ、箕面マイファーム。
みっつ、綾部の半農半X田んぼ。
今年は綾部の1000本プロジェクト田んぼはお借りしていない。それでも、半農半X研究所主任研究員として、脱穀とコナギ取りの手伝いはした。
静かな里の秋空の下で、塩見直紀さんと農作業をするのは至福の時である。
久しぶりに「里山ねっと・あやべ」に泊まれば思索が深まっていく。
考えるということは、穂を垂れた稲の下に潜り込んで実りを刈っていく行為に似ている。
ひたすら鎌を進めていけば、いつかは視界が開けることもある。霧が光に溶けこんでいくように。
今、僕が考えているのは、田中文脈研究所をどのように定本化していくか、という課題である。
塩見さんが提言している「一人一研究所のススメ」にしたがって設立した当研究所。その研究レポートは膨大な量になっている。400字詰め原稿用紙に換算すれば790枚を超えつつある。
定本化作業は地道にやるしかない。WEB上のテキストを縦書きに移しかえて写真をレイアウトしていく。田んぼに残されたコナギの根を一本一本掘って土を綺麗にしていくように。
時間がかかる。だが、この原稿を読んでくれる人はもっと時間と労力がかかるはずだ。できるだけ丁寧にやるしかない。
電通を早期退職して4年になる。書き連ねてきたことをひと繋がりにしていくと、分かってきたことがある。
僕は、半農半Xというコンセプトに導かれて、その背後に広がるコンテキスト(文脈)を探求するために動いているのだ。
さらに今年の半農には「善通寺田んぼ」という丸亀高校文脈も加わった。
また、夏の里山を流れる川でしかできない鮎釣りだって「半農」の文脈に繋がっている。水脈かもしれないが。
里山の川は農に直結している。川のそばには田んぼがあり畑がある。
半農半Xの基本的心構えである「センス・オブ・ワンダー(自然の神秘さや不思議さに目を見張る感性)」は川でも磨かれる。
僕の半農については、他人に分かるように説明する自信はある。
では半Xはどうか?
僕は半農半コンテキスターです、と言い続けてきた。
コンテキスターとは何か?
文脈家です。文脈を繋いで物語をつくる者です。詳しくはグーグルで「コンテキスター」と検索してみてください。そこには僕しかいませんから。これも僕の自己紹介の一パターンだ。
それはそれで自分の中では納得感がある。だが、他人が分かってくれているのかどうかは自信がなかった。
そんな気持ちのまま、相変わらず自由を友として動き回っていた。
そして、文脈原稿を整理しているうちに、自分の半Xの新しい考え方が見えてくる。
僕の半Xとは何か?
XはあくまでもXなのだ。
それは未知でありクロスである。関係性であり交錯である。
僕は「半農半X家」。
半農半Xか? と疑問形に聞こえないように発音しないと。
半農、すなわち小さな農をベースにして自分の天職、すなわちXを探していくのが「半農半Xという生き方」である。
たとえば、「半農半歌手」「半農半NPO」「半農半医」「半農半祈り」……。
ならば、Xを天職とする生き方があってもいいはずだ。
関係性を探究して、その交錯を楽しむ生き方。それを型として工作していく生き型……。
フミメイと呼ばれはじめてから現在まで、様々なことを見て聞いて、書いたりしゃべったりしてきたのは「半農半X家」としてのミッションだったのかもしれない。
上山棚田団での関係性は、右も左も上も下も交錯して〝複雑形X〟の宝庫になっている。
そこでのフミメイは固有の「楽しいことは正しいこと」というプリンシプルにしたがって動いていくしかない。
マイファーム箕面のフミメイ農園は15平米の有機栽培を文系百姓として続けている。
そこで始まった野菜縁脈は、自然栽培も交錯して様々な関係性を耕作しつつある。京都の日吉、島根の松江や山王寺と〝草の根X〟のエリアは拡大している。
綾部のXは明解だ。そこには塩見直紀さんがいるから。
田んぼを渡る風は、一定の方向へ吹き抜けていく。それは未来圏から吹いてくる颯爽とした風である。
〝あとから来る者のためのX〟が綾部にはある。
「半農半X家」という妙な言葉を主任研究員が勝手につくっていいものかどうか、疑問は残る。
ただ、Xに何をあてはめるかは〝使命多様性〟に基づき、人それぞれである。
ならば、Xに〝クロスして交錯すること〟をあてはめる変わり者がいてもいいはずだ。
「半農半Xカー」であるフミメイ号は、この4年間で86000キロを走破している。地球を2周以上。
「半農半X家フミメイ」は動いた距離に裏付けられている。自分の足と手でXを掴み取るための研究はしてきたつもりである。
君は半農半Xか? はい、自分は半農半X家であります。
二度とない人生だから
つゆくさのつゆにも
めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめてみつめてゆこう
(『詩集 二度とない人生だから』坂村真民)
最近、当研究所のレポートはやたらと長いものになっていた。
ブログという情報発信方式では、どうしても自分の語りたいことを一方的に届けることになってしまう。それでは読む方も大変だ。
文脈研究所の設立当時は、適度な原稿量であったと思う。原点に戻ろう。
今月は、定本・田中文脈研究所の章立て案をレポートして脱稿なのだ。
第一章 脱藩カウントダウン
第二章 《自立》する日々
第三章 そして311、アンガージュマンする日々
第四章 交錯し考察する日々
第五章 転がり続けて物語る日々
第六章 踊り場の日々
(以下未定)




















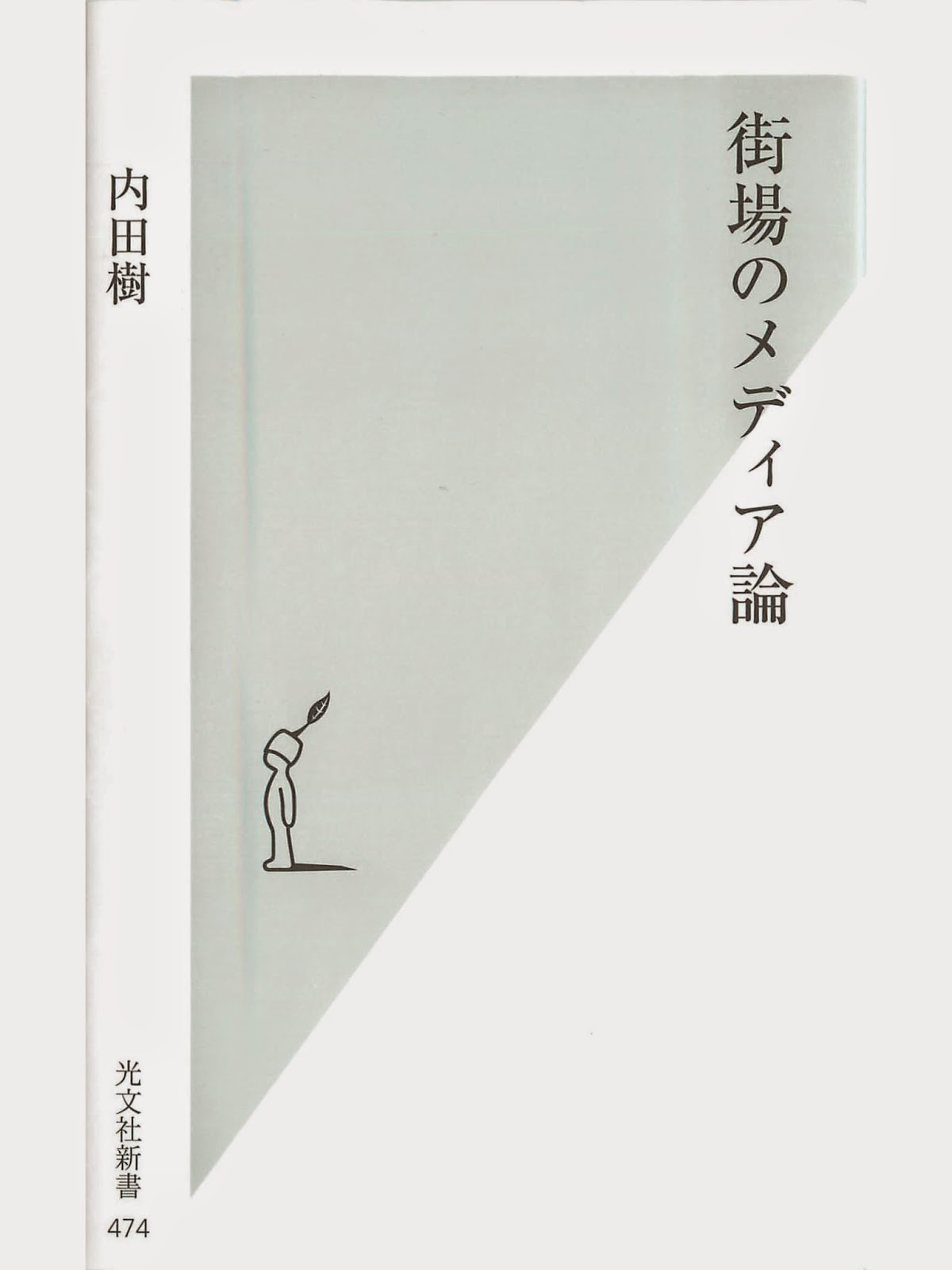



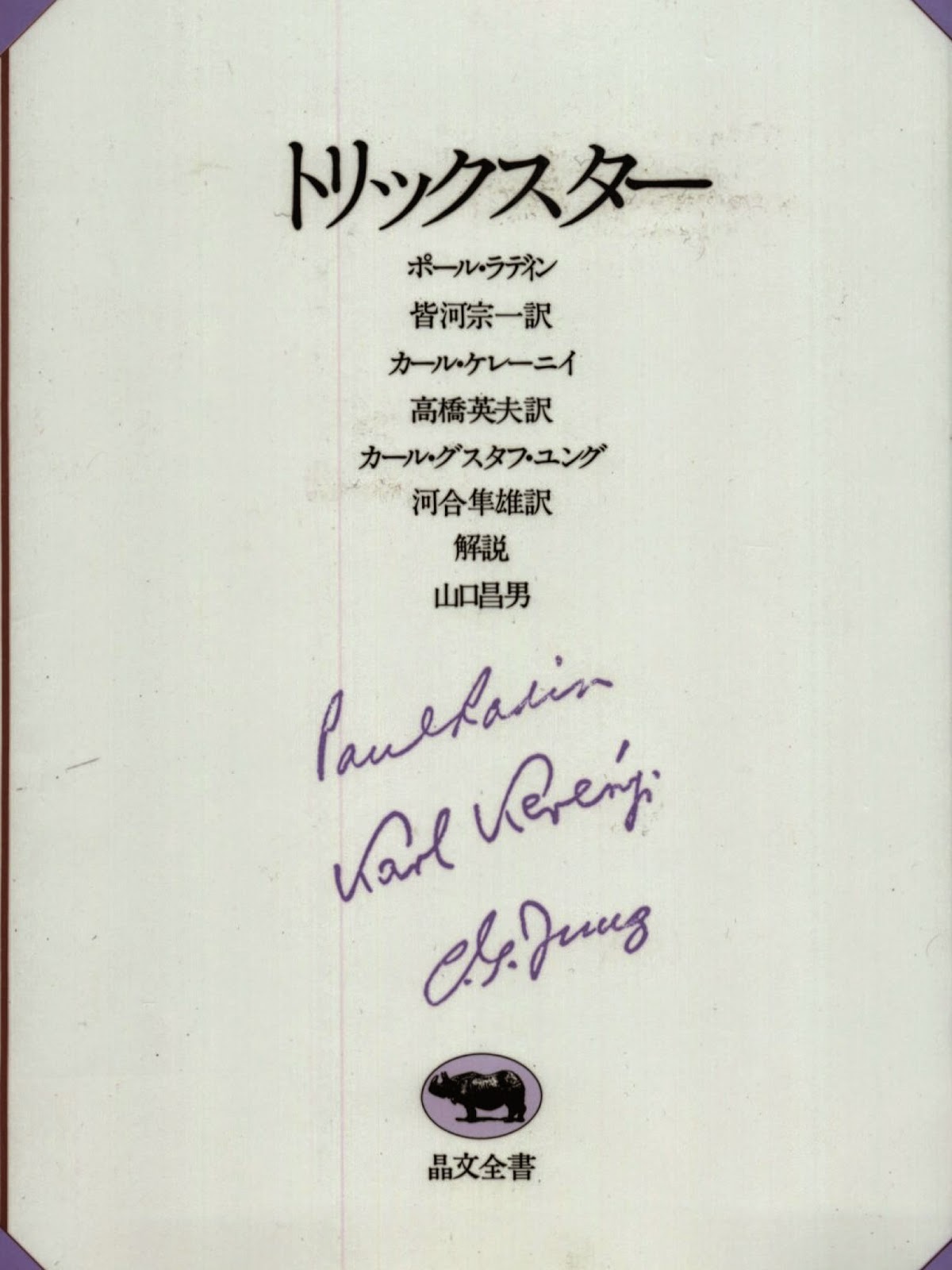





.JPG)






















